|
|
|


 |
小学校ホームページの魅力とは? Part 1 |
子供たちが見せる「顔」
| 飯島 |
 |
小学校のホームページをめぐる、魅力とそしてその可能性について少しみなさんからお話をうかがいたいと思います。私も日頃、企業や自治体のホームページのデザインをチェックしたり、コミュニケーションの改善ということを見ているのですが、小学校のホームページというのは、企業、自治体などのホームページにはない魅力があるのではないかと思っています。昨日も、県代表全部を徹夜で見ていて感じたのは、その土地ならではの活き活きとした営みや、その小学校独特の空気感を感じるとともに、見ていて優しい気持ちになるんですね。これは他のサイトにはない魅力ではないかなと思います。
|
| 高畑 |
 |
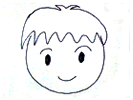 私は、絵で描かせていただきました。これは「顔」です。小学校ホームページの魅力といえば、学校での子どもたちの顔が見られるというのが大きな魅力なんだろうなと思っています。ただ、学校によっては、プライバシーの保護ということで顔を映さないように後ろからの写真を掲載しているところもあります。先生たちにとっては悩みどころなんですけれども、保護者の1人としては、子どもたちの顔が見たいという希望がありますね。なぜかというと、子どもというのは家で見せる顔と学校にいる顔というのはたぶん違うんですよ。子どもの顔を家で見ているのと、学校で友だちと遊んでいる顔、勉強している顔、真剣な顔だとか、学校での顔は違うわけです。そういった意味で、日頃見えない顔がホームページの中で見られればいいなと思っております。
たとえば、児童8名のある小さな小学校では、卒業生2人を送り出すのに毎日毎日カウントダウンをしていて、その卒業生を送り出す在校生が卒業生への思いを顔写真と一緒につづっていました。最後には、卒業式で泣いた顔が表情としてしっかり出ています。顔の表情がしっかり見えるということは受け取る側として感じ方が違うと思うんですね。そういった意味で、顔というものをあげました。 私は、絵で描かせていただきました。これは「顔」です。小学校ホームページの魅力といえば、学校での子どもたちの顔が見られるというのが大きな魅力なんだろうなと思っています。ただ、学校によっては、プライバシーの保護ということで顔を映さないように後ろからの写真を掲載しているところもあります。先生たちにとっては悩みどころなんですけれども、保護者の1人としては、子どもたちの顔が見たいという希望がありますね。なぜかというと、子どもというのは家で見せる顔と学校にいる顔というのはたぶん違うんですよ。子どもの顔を家で見ているのと、学校で友だちと遊んでいる顔、勉強している顔、真剣な顔だとか、学校での顔は違うわけです。そういった意味で、日頃見えない顔がホームページの中で見られればいいなと思っております。
たとえば、児童8名のある小さな小学校では、卒業生2人を送り出すのに毎日毎日カウントダウンをしていて、その卒業生を送り出す在校生が卒業生への思いを顔写真と一緒につづっていました。最後には、卒業式で泣いた顔が表情としてしっかり出ています。顔の表情がしっかり見えるということは受け取る側として感じ方が違うと思うんですね。そういった意味で、顔というものをあげました。
|
| 飯島 |
 |
豊福さんはご両親が教師だとおっしゃっていましたが、私も実は教師のせがれなんですね。私の母はもう亡くなっているんですけれども、日本で初めて小学校の子ども電話相談というのを始めたんです。電話を受けるときには、先生ではなくただのおばさんとして出るわけなんです。教師として対面しているのと、電話相談室のおばさんとして対面しているのとでは、子どもが全く違っていたということを話していました。子どもも私たちも多様な顔を持っているわけですけれども、その多様な顔がインターネットといった技術を使って新しい顔が見えるんではないかと思いますね。今おっしゃっていた1人1人の個性であるとか、1人1人の活き活きとした生の姿であるとかが見える唯一のメディアだろうというふうに思います。 |
新しい「ふれあい」を求めて
| 関根 |
 |
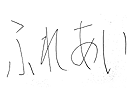 キーワードは「ふれあい」です。私は、現場の人間なので、子どもたちとは毎日たくさん触れ合っているのですが、そういう直接的なふれあいとはまた別の意味のふれあいです。うちの学校は子どもからメールを募集して、来たら載せてあげるというページがあるのですけれども、そこに卒業生の父兄からメールが来たことがあるんですね。卒業した生徒の保護者の方とコミュニケーションが取れるというのはホームページのおかげだと思います。卒業生からも来ますし、教師と教師のふれあいもホームページのおかげで生まれます。 キーワードは「ふれあい」です。私は、現場の人間なので、子どもたちとは毎日たくさん触れ合っているのですが、そういう直接的なふれあいとはまた別の意味のふれあいです。うちの学校は子どもからメールを募集して、来たら載せてあげるというページがあるのですけれども、そこに卒業生の父兄からメールが来たことがあるんですね。卒業した生徒の保護者の方とコミュニケーションが取れるというのはホームページのおかげだと思います。卒業生からも来ますし、教師と教師のふれあいもホームページのおかげで生まれます。
|
| 飯島 |
 |
今、おっしゃられた卒業生の父兄の方からというお話でしたけれども、中の文面や言葉使いも、日頃学校での父兄と先生との会話とは違うものになっているのでしょうか。
|
| 関根 |
|
ぜんぜん違います。昔なじみのお友だちに書くような、すごく親しみの持てる、独り言のような書き方でした。そのときは卒業式の後だったんですけれども、「とってもよかったわ」といった、独り言のような、親しい友だちに聞いてもらうような書き方が非常に印象的でした。
|
| 飯島 |
|
なるほど。ありがとうございます。ここでもメールコミュニケーションでは、新しい文体が生まれていることと、新しい回路が生まれているということがわかりますね。 |
コミュニケーションの喜びを子供たちにも
小学校と卒業生、地域とのつながり
| 豊福 |
 |
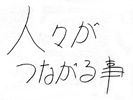 私は「人々がつながること」と書きました。 私は「人々がつながること」と書きました。
私は大学の講義の中で、自分の母校のホームページを評価するという課題を出しています。すると、卒業して間もない中学校や高校に対しては、かなり辛口のコメントが多いのですが、小学校に対する思いはもう少し違っていて、懐かしさが前面に出てくるようです。「あぁ、まだこの学校とつながっているんだ」ということを確認するわけですね。もし、自分の出身小学校のホームページがあれば、「自分は母校に何が出来るだろう?」とふと考えるきっかけになるんじゃないかと思うのです。
別のケースでは、保護者が転校先を決めるのにホームページをよく見ているという話がありました。学校のホームページで、普段こういうことやっていますよ、というアピールがあると、一緒に参加して学校を作ろうという立場がより鮮明に出てくる気がします。
もうひとつ、学校の近所の人々はふだん遠巻きに「学校では一体何をやってるの?」と思っているわけです。学校側は学区の防犯対策や地域の協力者を発掘する必要があるのですが、学校だけでできることは限られるので、いざというとき地域が学校の味方になるのか、敵になるのかで、大きな違いが出てきます。ホームページを通して普段から情報が伝えられていれば、学校に対する不信感は消えますし、いろんな人がお互いにつながり合うきっかけになると思いますね。
|
| 飯島 |
 |
地域社会とつながるという大きな役割があるという大きなお話でした。今回の県代表の中で、地域ポテンシャルも含めて視野に入れているというところはまだまだ少ないと思うんですけれども、いくつかの萌芽は見えてきていると思います。いま、コミュニケーションをめぐる危機管理、地域の危機管理であるとか、そういう役割が小学校のホームページにはあるんだということは、私も感じました。それから、子どもたちひとりひとりが自分の頭で考えるというところを保障しているところが、ホームページならでは、ではないかと思っております。よく外から見ると、「子どもたち」という、ひとつのくくりのなかで意識が働いてしまいますね。でも、ホームページだとひとりひとりが自分なりの考え方で表現をしている。世の中が子どもたちを見る目が十把一絡げでなくなる、ひとつの契機になるのかなと思います。
|
差別化を通して、学校のクオリティーアップを
| 豊福 |
 |
 もともとアメリカにはチャータースクール*の発想がありますね。教師、保護者の有志がこういう学校を作りたいというコンセプトを出して、学校設立運営のチャーター(許可)を取るという仕組みです。日本でもようやく実現のめどが見えてきました。学校自由選択制を採用する自治体も増えています。そうなると、全国どこでも同じ学校・同じ教育サービスでなくて、学校独自の教育方針や教育成果がよりシビアに問われるようになります。公立学校といえど、児童生徒集めを真剣に行わないと学校が立ち行かなくなってしまうので、学校側からのアピールはより重要度を増してくるでしょう。当然、競争が全てではありませんが、学校同士が互いに切磋琢磨することで、それぞれのクオリティーや魅力がアップしていくだろうと思います。 もともとアメリカにはチャータースクール*の発想がありますね。教師、保護者の有志がこういう学校を作りたいというコンセプトを出して、学校設立運営のチャーター(許可)を取るという仕組みです。日本でもようやく実現のめどが見えてきました。学校自由選択制を採用する自治体も増えています。そうなると、全国どこでも同じ学校・同じ教育サービスでなくて、学校独自の教育方針や教育成果がよりシビアに問われるようになります。公立学校といえど、児童生徒集めを真剣に行わないと学校が立ち行かなくなってしまうので、学校側からのアピールはより重要度を増してくるでしょう。当然、競争が全てではありませんが、学校同士が互いに切磋琢磨することで、それぞれのクオリティーや魅力がアップしていくだろうと思います。
|
| 空白 |
 |
*チャータースクールとは
公立学校としての運用経費の支給を受けるが、学校運営方針・人事・カリキュラム等について直接教育委員会の規制を受けない学校
|
|

