|
|
|


 |
小学校のホームページはこう変わる! |
学校のことをもっと知ってもらう努力
「責任」ということの意味
| 飯島 |
 |
後半の話は応答可能性が高まってくるということですね。この応答可能性を英語で言うとレスポンシビリティー、英語を日本語に訳すときは責任となりますが、責任の中身はこの応答可能性のことなんですね。小学校のコミュニケーションの中で、応答し合うという習慣ができますと、コミュニケーション能力であるとかプレゼンテーション能力が発達してくる。その下地は、1日の中で何度も応答してくというところから始まるのではないかなと思いますね。応答しようするところに責任が果たせる要因が出てくるのではないかなと。これはコミュニケーション能力の根幹に関わることで、日本の社会では応答し合うということをあまりしていなかったと思うんです。これまでの小学校のコミュニケーションの場面でも同様です。その子どもたちとの応答が高まるということは、大きな可能性があるのではないかなと、お話を聞いていて思いました。
|
地域の情報センターとしての学校ホームページ
子どもは人類の父親である
情報発信=情報受信
| 上田 |
 |
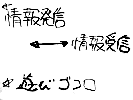 僕は、可能性ということでいうとふたつあって、ひとつは「情報発信=情報受信」という言葉なんです。ホームページというのは、どうしても情報発信の場ということでとらえられがちなんですけれども、実は情報を発信すると同時に、受信する場なんですね。具体的な事例でいうと、小学校ではないですけれども、広島の中学生が英語で原爆についてのホームページを作ったら、アメリカからいろんな中学生から問い合わせがあって、そこから交流が始まったんですね。ホームページに自分たちの地域のことを情報として発信することによって、今度はアメリカで原爆についてどのようなことを考えているか、どんどん受信する場が作られた。受信していくということを意識していくと情報発信の意義がどんどん広がっていくように思えるんですね。
あるいは、鹿児島県に沖永良部島という島があります。その島にある唯一の高校、沖永良部高校がウミガメの生態のライブ中継をしています。もうすこししたら英語のホームページもできるのですが、そうすると世界中の人たちがここにやってくる。実は高校生たちは、沖永良部の自然のことはあまり知らないんですね。でも、自分たちがその映像を発信することによって、世界中の人たちから質問攻めにあうわけです。そうなると一生懸命調べ始める動きが起こるわけです。恥ずかしい答えはできないので、どんどん勉強したりというようなことが、現実に起きているというのが面白いと思うんです。
もうひとつは、「遊び心」という言葉ですけれども、どうしても評価基準とかの話になってくると、みんなが同じレベルを目指すようになってくる。いろんな可能性を拾えるような評価基準を作っていくこともとても大事なことだと思うのですが、評価基準を覆してしまうようなページ作りをしていただけたら面白いなと思いますね。「こんな手があったんだ、評価基準を変えなきゃいけないね」というような遊び心があるものが見たいですね。 僕は、可能性ということでいうとふたつあって、ひとつは「情報発信=情報受信」という言葉なんです。ホームページというのは、どうしても情報発信の場ということでとらえられがちなんですけれども、実は情報を発信すると同時に、受信する場なんですね。具体的な事例でいうと、小学校ではないですけれども、広島の中学生が英語で原爆についてのホームページを作ったら、アメリカからいろんな中学生から問い合わせがあって、そこから交流が始まったんですね。ホームページに自分たちの地域のことを情報として発信することによって、今度はアメリカで原爆についてどのようなことを考えているか、どんどん受信する場が作られた。受信していくということを意識していくと情報発信の意義がどんどん広がっていくように思えるんですね。
あるいは、鹿児島県に沖永良部島という島があります。その島にある唯一の高校、沖永良部高校がウミガメの生態のライブ中継をしています。もうすこししたら英語のホームページもできるのですが、そうすると世界中の人たちがここにやってくる。実は高校生たちは、沖永良部の自然のことはあまり知らないんですね。でも、自分たちがその映像を発信することによって、世界中の人たちから質問攻めにあうわけです。そうなると一生懸命調べ始める動きが起こるわけです。恥ずかしい答えはできないので、どんどん勉強したりというようなことが、現実に起きているというのが面白いと思うんです。
もうひとつは、「遊び心」という言葉ですけれども、どうしても評価基準とかの話になってくると、みんなが同じレベルを目指すようになってくる。いろんな可能性を拾えるような評価基準を作っていくこともとても大事なことだと思うのですが、評価基準を覆してしまうようなページ作りをしていただけたら面白いなと思いますね。「こんな手があったんだ、評価基準を変えなきゃいけないね」というような遊び心があるものが見たいですね。
|
スクールディレクションという感覚
| 飯島 |
 |
さきほど、「踏み台」という言葉が出ましたが、たぶん飛躍、スプリングボードとして飛躍させるのは私たちの想像力だろうと思います。想像力を刺激すること、そのこと自体がホームページの主要な機能ではないかなと思っております。そして、想像力をどのように刺激するかということは、実は小学校の中だけでなく、多くの力をウェブは借りることができるんだということです。ウェブの時代の事例ではありませんですけれども、今となっては有名な富良野というところがあります。富良野のラベンダー畑の写真は前田信三さんという東京の写真家が撮ったんですね。地元の人があまり知らない魅力をひとつの写真家の目、もうちょっと突っ込んで言えば、美に対する目が発見した。ふらりと行った写真家が素敵な映像をギフトしてくれるかもしれないと思います。稀人(まれびと)だから、旅人だからこそ見えてくる世界があると思います。
学校では、他の学校から新しい校長先生がやってきて、その学校を客観的に見ることができる場合があります。僕は、そうした役割に特化したスクールディレクターというような職能が必要になってくるんじゃないかなという風に思っています。子どもたちの授業を受け持つだけではなくて、学校全体の企画であるとか、学校がどこへ行こうかということも含めて、その中でスクールディレクションを、あるときは中央に折衝に行ったり、ビジョンをホームページで訴えたりする。たまたま先ほど事例に出てきた、古川校長は先生自身がスクールディレクションということを行っているわけですけれども、全国の多くの小学校にはスクールディレクションといった感覚をもった人が必要なのではないかと思います。
今日のお話を私なりにまとめさせてもらうと、小学校ホームページは、メディアとしての可能性が多分にあるという風に思いました。それからホームページを作るというプロセスに多くの人が関わることによって、今までなかった新しい色合いが出てきて新しいつながりが出てくると思います。そのつながりの中で、コミュニティーとしてのホームページということですが、住人がいるわけですから、その人たちが日々活き活きと暮らしている姿をホームページ上に表わすことによって、コミュニティーのイメージが見えてくるのではないかと思います。また、松本先生からは拠点というキーワードを頂きました。私たちが生きていく場として、コミュニティーをもっと深めたり、自然環境と結びついた、自分が身を委ねて、生きていく、安全を確保して生きていく場としてのホーム作りということだろうと思います。
|
|

