|
|
|


 |
小学校ホームページの魅力とは? Part 2 |
記憶装置としてのホームページ
美しい庭園を造るということ
| 上田 |
 |
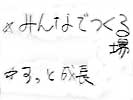 僕は2つなんですけれども、「みんなで作る場」と「ずっと成長」というキーワードを書いてみました。みなさんがおっしゃったこととすごく近いんですが、僕は県代表校のホームページを見せていただいて感じたことは、みんなで作っているホームページは心にぐっと来るんですよね。みなさんが先ほどからおっしゃっている喜びが伝わってきたりですとか、地域と生徒さんと先生と家族がつながっていたりですとか。そういったことは、ちょっとした言葉使いだったりですとか、小さな絵だったり、写真だったりから、伝わってくるものです。デザインがいいとか悪いとかということではなくて、全体の雰囲気でみんなで作っているんだろうなというのが、すごくよくわかるんですよね。そうすると、だんだんここに行ってみたいなと思うようになったり、この地域の町を歩いてみたいなと思うようになったり、場の感覚というのがどんどん呼び覚まされてくるんですね。
昔からよく言われることですが、ホームページを大きく分けると看板型とお庭型に分けられるんですね。写真を動かして、テキスト置いて、あとはおしまい。今は減っていますけど、昔の企業のホームページはほとんどがそうで、まず作って出すことが大事ということでぜんぜん更新しない。でも、ホームページっていろんな人が集まって、見に来る場所なわけですから、むしろお庭みたいなかたちがいいんですね。季節、季節によって、気がついた人がちょっとずつ手入れをして、成長したり変化するお庭型。僕たちも作るときには、なるべく手が入っているような感じのホームページを心がけています。それはそれで大変なんですけれどね。県の代表校になっていたり、昨年大賞を取られた大森小学校もすごく手が入っているような感じがして、とてもいい。それが小学校ホームページの大きな魅力だと思います。 僕は2つなんですけれども、「みんなで作る場」と「ずっと成長」というキーワードを書いてみました。みなさんがおっしゃったこととすごく近いんですが、僕は県代表校のホームページを見せていただいて感じたことは、みんなで作っているホームページは心にぐっと来るんですよね。みなさんが先ほどからおっしゃっている喜びが伝わってきたりですとか、地域と生徒さんと先生と家族がつながっていたりですとか。そういったことは、ちょっとした言葉使いだったりですとか、小さな絵だったり、写真だったりから、伝わってくるものです。デザインがいいとか悪いとかということではなくて、全体の雰囲気でみんなで作っているんだろうなというのが、すごくよくわかるんですよね。そうすると、だんだんここに行ってみたいなと思うようになったり、この地域の町を歩いてみたいなと思うようになったり、場の感覚というのがどんどん呼び覚まされてくるんですね。
昔からよく言われることですが、ホームページを大きく分けると看板型とお庭型に分けられるんですね。写真を動かして、テキスト置いて、あとはおしまい。今は減っていますけど、昔の企業のホームページはほとんどがそうで、まず作って出すことが大事ということでぜんぜん更新しない。でも、ホームページっていろんな人が集まって、見に来る場所なわけですから、むしろお庭みたいなかたちがいいんですね。季節、季節によって、気がついた人がちょっとずつ手入れをして、成長したり変化するお庭型。僕たちも作るときには、なるべく手が入っているような感じのホームページを心がけています。それはそれで大変なんですけれどね。県の代表校になっていたり、昨年大賞を取られた大森小学校もすごく手が入っているような感じがして、とてもいい。それが小学校ホームページの大きな魅力だと思います。
|
小学生からつながっている「今の自分」
| 上田 |
 |
 もうひとつのキーワードは「ずっと成長」です。これはすごく個人的な話なんですけれども、代表校のホームページを見てすごく羨ましいと思ったわけです。というのは、僕も自分の小学校を探して見に行くわけですけれども、僕は引越しが多くて三つの小学校に通っていたんですが、みんな看板型なんですよ。校歌が置いてあって、少し懐かしいなという雰囲気はあるんですけれども、更新したのはもう3年前? という感じですね。もしも自分の小学校のホームページが、大森小学校のような豊かなホームページだったら、自分の小学校と関係が切れないで今も自分が成長している感じがするんじゃないかなという気がしたんですね。それは自分が出た小学校が今もまだ元気で、なかなかそこに行くことはできないけれども、ホームページを通じて触れ合うことができる。それによって自分の成長を確認できる。それは卒業生にとっても大きな魅力になるんじゃないかなという風に思いました。 もうひとつのキーワードは「ずっと成長」です。これはすごく個人的な話なんですけれども、代表校のホームページを見てすごく羨ましいと思ったわけです。というのは、僕も自分の小学校を探して見に行くわけですけれども、僕は引越しが多くて三つの小学校に通っていたんですが、みんな看板型なんですよ。校歌が置いてあって、少し懐かしいなという雰囲気はあるんですけれども、更新したのはもう3年前? という感じですね。もしも自分の小学校のホームページが、大森小学校のような豊かなホームページだったら、自分の小学校と関係が切れないで今も自分が成長している感じがするんじゃないかなという気がしたんですね。それは自分が出た小学校が今もまだ元気で、なかなかそこに行くことはできないけれども、ホームページを通じて触れ合うことができる。それによって自分の成長を確認できる。それは卒業生にとっても大きな魅力になるんじゃないかなという風に思いました。
|
| 飯島 |
|
自分の小学校をクリックしてみるという行為はなかなかしないかもしれないですけれども、そこで楽しいホームページが展開されていると、誇りに思ったり、元気をもらったり、そういった効果があると思いますね。先ほど、上田さんが話していた庭の手入れみたいなことがありましたが、手入れをしていくということが一番労力と情熱が必要だと思うんです。 |
地球時間という時間感覚
| 飯島 |
 |
上田さんは、Think the Earthプロジェクトで、ホームページももちろん立ち上げておりますけれども、オルカライブという、シャチの生態をライブ中継している素敵なサイトも作っていますね。オルカライブとまでいかなくても、小学校の近くの山でクワガタライブでもセミライブでも、何でもできると思います。その土地に生きている動物や、子供たちも含めたライブでもいい。今回も九州の学校でメダカの動画を撮られていらっしゃった方がいました。生き物を観察するということはひとつの時計になるんですね。人間は本来、春夏秋冬という四季の中で生きているわけですけれども、普段は後からつけた時間観念、つまり24時間、1日、1週間、1か月、1年という感覚の中に住んでいる。学校の先生方はその中で、カリキュラムをこなさなければならないというような枠がありますが、もうひとつ、生き物を時計とする時間感覚をホームページまたインターネットを使って取り込めるのではないかなと思います。私たちの生活の中に、もうひとつの時計を組み込むチャンスなんです。Think the Earthでは地球と共鳴するというがひとつのコンセプトですけれども、もう一方で自分たちの足元にいる生き物たちと共鳴することが、小学校のホームページでは特に可能性があるのではないかなという風に思いました。
|
|

