
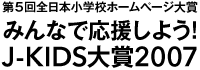
全体討論会:『ホームページをどのように活用していくか』
「地域情報ブログで見えた保護者の地域教育力」
 北海道斜里郡斜里町峰浜小学校
北海道斜里郡斜里町峰浜小学校
2005年経済産業大臣賞、2006年文部科学大臣賞受賞
北海道の知床に位置する、全校児童22名の小学校です。ホームページを始めたきっかけは、県外の児童を対象に行う山村留学でした。「外」の人が見る知床は、「中」にいては気づかない発見にあふれています。それを伝えようとすることなどから、内容が広がっていったのです。
J-KIDS大賞の存在を知ってから、それまでは漫然と取り組んでいたホームページも、読む人のことを考えてつくるようになりました。地域の人々も、参加してくれます。畑に丹頂鶴が来ると携帯で写真を撮り、送ってくれるのです。活動の中で忘れがたいのは、インターネットで子どもたちの出会いがあったこと。ブログをきっかけに、東京の辰巳小学校と交流が始まり、「サケの稚魚を放流する」活動を一緒に行いました。知床から東京へ出向き、子どもたちが対面した瞬間は、今思い出しても涙がこみ上げるような風景でした。インターネットにより、学校を訪れなくても峰浜小のことを知っている人が増え、ネットワークも広がりました。応援してくれる人がいるということを、実感しています。
「パソコンに委員会の活動〜他校との交流活動を中心にして〜」
 愛知県一宮市立瀬部小学校
愛知県一宮市立瀬部小学校
2006年経済産業大臣賞受賞
昨年、賞はいただきましたが、特別に自慢する所なんてないんです。これからお話するのも、どこの学校でも行っていることだと思います。ひとつはパソコン委員会をつくり、子どもたちがホームページづくりに参加していること。もうひとつはブログを通じた他校との交流を進めていることです。パソコン委員会は、情報があふれる中で、しっかり自分の意見を表し、発信できる子どもになってほしいとの願いから。今では、子どもたちが各自記事集めノートを持って、取材し書いています。みんなで、感動をつくっている気がします。
ただ発信するだけではつまらないので、全国から交流先を探し、どんどんコメントとトラックバック、あるいはメールでアプローチしています。パソコン委員会以外の児童に向けては、ホームページに関するクイズを出して、認知に努めるなどイベントも行い、楽しみながら伝えてます。多くの人が懸念されるようにインターネットは確かにマイナス面もあります。、けれどもプラスの方がはるかに大きいと感じています。
「教材の学びと学校ホームページの連携で相乗効果を」
 熊本県人吉市立中原小学校
熊本県人吉市立中原小学校
2006年J-KIDS大賞受賞
ホームページの可能性については、ここにおられる皆さんもいろいろ感じながらも、多忙なために、なかなか更新する時間がとれない、というのが実情だと思います。そこで、当校で実践しているのが、学習過程の中に、ホームページを活用して「伝える」という手段を、あらかじめ設定して取り組むことです。
まず、教科の中の年間指導計画と単元を洗い出します。そこから、対応できそうな教科と単元を教師が掴み取ることがポイントで、それを元に年間指導計画を修正していきます。教科の学びを総合で実践するという横断的な学習方法です。国語のほか、例えば家庭科で「夢の給食メニュー」と食育の実践、図工の作品発表など、さまざまな展開があるでしょう。その成果をホームページで公開すると、反応や第三者評価を得ることもでき、子どもたちの励みにもなります。J-KIDS大賞を受賞したことも、子どもたちが企画から全て携わり、記事に仕上げました。近年懸念されている子どもたちの読解力不足を克服する手がかりとしても、活用できると思います。誰かに見て、読んでもらいたいという気持ちから、子どもたちは学んでいるのです。
あとがき
子どもたちがいきいきと学び成長していく様子を、みんなに知ってもらいたい。ホームページづくりを学びの場として活用していきたい。保護者や地域など、双方向の交流を深めていきたい。あるいは、全国の小学校同士でネットワークを築き、ともに学んでいきたい……。小学校ホームページの根底にあるのは、よりよい学校となることを目指した、きわめて前向きな視点です。
子どもたちは未来そのもの。元気あふれるエネルギーは、社会にとって希望の光でもあるのです。少子化という大きな課題を抱えた現代社会では、子どもと社会との溝は、深まっていく傾向にあります。そうした現状において、学校ホームページは、社会全体で子どもの成長を支援していくきっかけとなる、小さな一歩でもあるのです。
今回のサミットで語られたさまざまな話題は、次へのバトンです。参加されたみなさんが成果と課題と持ち帰り、それぞれのホームページに反映させていく。そして、それを見た学校や社会が反応し、また善処していく。この繰り返しこそが、子どもと社会との間にあるギャップを埋めていく、現実的な手だてとなることでしょう。
J-KIDSサミット報告:石黒知子
 リポート目次へもどる
リポート目次へもどる
2005年経済産業大臣賞、2006年文部科学大臣賞受賞
 |
J-KIDS大賞の存在を知ってから、それまでは漫然と取り組んでいたホームページも、読む人のことを考えてつくるようになりました。地域の人々も、参加してくれます。畑に丹頂鶴が来ると携帯で写真を撮り、送ってくれるのです。活動の中で忘れがたいのは、インターネットで子どもたちの出会いがあったこと。ブログをきっかけに、東京の辰巳小学校と交流が始まり、「サケの稚魚を放流する」活動を一緒に行いました。知床から東京へ出向き、子どもたちが対面した瞬間は、今思い出しても涙がこみ上げるような風景でした。インターネットにより、学校を訪れなくても峰浜小のことを知っている人が増え、ネットワークも広がりました。応援してくれる人がいるということを、実感しています。
「パソコンに委員会の活動〜他校との交流活動を中心にして〜」
2006年経済産業大臣賞受賞
 |
ただ発信するだけではつまらないので、全国から交流先を探し、どんどんコメントとトラックバック、あるいはメールでアプローチしています。パソコン委員会以外の児童に向けては、ホームページに関するクイズを出して、認知に努めるなどイベントも行い、楽しみながら伝えてます。多くの人が懸念されるようにインターネットは確かにマイナス面もあります。、けれどもプラスの方がはるかに大きいと感じています。
「教材の学びと学校ホームページの連携で相乗効果を」
2006年J-KIDS大賞受賞
 |
まず、教科の中の年間指導計画と単元を洗い出します。そこから、対応できそうな教科と単元を教師が掴み取ることがポイントで、それを元に年間指導計画を修正していきます。教科の学びを総合で実践するという横断的な学習方法です。国語のほか、例えば家庭科で「夢の給食メニュー」と食育の実践、図工の作品発表など、さまざまな展開があるでしょう。その成果をホームページで公開すると、反応や第三者評価を得ることもでき、子どもたちの励みにもなります。J-KIDS大賞を受賞したことも、子どもたちが企画から全て携わり、記事に仕上げました。近年懸念されている子どもたちの読解力不足を克服する手がかりとしても、活用できると思います。誰かに見て、読んでもらいたいという気持ちから、子どもたちは学んでいるのです。
あとがき
 |
 |
J-KIDSサミット報告:石黒知子